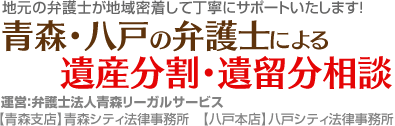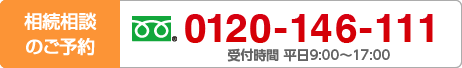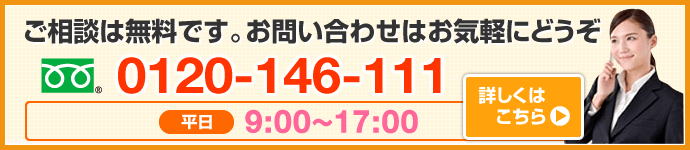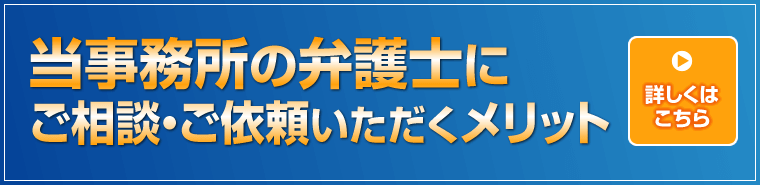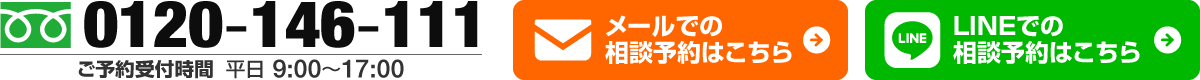1 大規模な遺産分割とは?

大規模な遺産分割とは、明確な金額などの基準・定義があるわけではありませんが、一般的な遺産分割よりも遺産の総額がはるかに大きく、遺産の内容も多岐に渡って複雑となる相続手続を指します。
通常は、遺産の総額が数億円から数十億円以上の遺産分割がこれに該当し、預貯金以外の不動産(収益不動産や農地なども)や、株式・有価証券、事業用資産など、遺産分割が難航する財産が多く含まれている傾向があります。
また、遺産の額が大きいがゆえに相続人同士の対立が激しく、特定の相続人が生前に多額の贈与を受けているなど関係性が複雑化しているケースも多いです。
相続人同士の対立が激しい中で、複雑かつ多岐に渡る遺産を適切に分割するためには、専門的な知識と多大な労力と時間が必要となります。
したがって、大規模な遺産分割では、通常の遺産分割とは大きく異なる対応が必要となります。
2 大規模な遺産分割でよくあるトラブル
(1)遺言書の有効性・不平等性に関するトラブル
遺産の額が大きいがゆえに、一人の相続人に全てを相続させる、あるいは大部分を相続させる内容の遺言書が遺されていた場合には、その遺言書の有効性が争われることが少なくありません。
また、法律に則って有効に作成された遺言書であっても、内容が不平等であることからトラブルに発展することもあります。
遺言書が無効となる例として、遺言者が認知症などで判断能力が低下している状況で作成された遺言書は、遺言能力がなかったとして無効となる可能性があります。
大規模な遺産を巡る場合、遺言能力があったかどうかが激しく争われ、医学的見地から争う「遺言能力鑑定」が行われることもあります。
また、自筆証書遺言では、法で定められた要件(内容全文、日付、氏名の自書、押印など)が満たされていない方式不備の場合には、無効となります。
さらに、特定の相続人に脅迫されたり、だまされたりして、故人の意思とは異なる内容の遺言書が作成された場合、取り消しや無効の対象となります。
遺言書の不平等性に関するトラブルとしては、特定の相続人(例えば家業を継いだ長男など)に、資産の大半を相続させる内容の遺言書が作成されるケースがあり、他の相続人は、自身が不当に排除されたと感じ、感情的な対立につながることが多いです。
兄弟姉妹以外の法定相続人(配偶者、子、直系尊属など)には、最低限の取り分として「遺留分」が法律で保証されていますので、遺言書によって遺留分が侵害された場合、遺留分権利者は多くの遺産を受け取った相続人に対して遺留分侵害額請求を行うことになります。
さらに、故人が特定の相続人に多額の生前贈与を行っていたにもかかわらず、遺言書でさらに多くの財産を相続させる内容だった場合、他の相続人から不満が出ることもあります。
この場合、特別受益(一部の相続人が受けた生前贈与など)の持ち戻しを巡って、生前贈与された多額の遺産の評価方法や金額が争点となることがあります。
(2)収益不動産や農地の遺産分割トラブル
収益不動産は、評価額や評価方法を巡って、よく争いが起こります。
不動産の遺産分割をするには、不動産の資産価値である評価額を算定しなければなりません。
そして、不動産の評価額を算定する評価方法は複数あり、どれを採用すべきかという決まりはなく、かつ、収益不動産の評価方法は複雑です。
評価方法が異なれば当然、算出される不動産の評価額は変わるため、どれを採用するかで争いに発展するわけです。
さらに、収益不動産を誰が相続するのかという問題とともに、収益不動産の家賃の分配をどうするか、税金や維持費用(修繕、保険、管理費など)の負担をどうするかでも紛争が発生します。
農地は、遺産分割協議が難航する・相続手続きが複雑になる代表的な遺産です。
被相続人が行っていた農業を継ぐ者がいない場合は、農地を相続することを希望する者もおらず、相続人間で不要な農地の押し付け合いとなって、遺産分割協議が難航してしまいます。
農地は簡単には売却できませんので、農地を相続することを希望する者がいない中で、法定相続分で分割しようと試みても、売却してその売却代金を分けるという遺産分割方法(換価分割の方法)を取ることが困難となります。
また、農業を継ぐ者がいて、その者が全ての農地を相続し、他の相続人が相続する財産は(ほとんど)ないという遺産分割では、他の相続人が納得しない場合は当然あります。
(3)株などの金融資産の遺産分割トラブル
株などの金融資産をめぐる遺産分割のトラブルは、不動産と同じく、評価方法、分割方法という点で発生します。
特に株式は、不動産と同じく分割が難しいため揉めやすい傾向があります。
株式の評価方法について、上場株式は客観的な株価があるため、評価自体は比較的容易です。
しかし、遺産分割時の株価は常に変動するため、どの時点の株価で評価するかによって相続人間に不公平感が生じ、争いの原因となることがあります。
非上場株式(自社株)は、市場価格がないため、客観的な評価が難しく、評価方法を巡ってトラブルになりやすいです。
とくに後継問題が絡む場合には、経営権に直結する重要な資産であるため、後継者と他の相続人の間で争いが起きやすい傾向があります。
そして、株式は、預貯金のように金額で簡単に分けられないため、相続人全員の同意を得るのが難しい場合があります。
遺産分割の不均衡を調整するために特定の相続人が株式を相続し、その代償として他の相続人に金銭を支払う代償分割が利用されます。
しかし、その代償金の額について合意できず、トラブルになることもあります。
(4)会社の承継トラブル
相続において、会社の承継を巡るトラブルは、後継者や株式の行方、相続税負担などを原因として発生するケースがあります。
主なトラブルとその原因は、株式の分散による経営権の不安定化によるものです。
経営者が遺言書を遺していないと、会社の株式は法律に基づき、複数の相続人に均等に分配される可能性があります。
そして、株式が分散すると、後継者が十分な議決権を確保できず、経営の主導権を握れなくなったり、親族の派閥争いによって経営が混乱したりする恐れがあります。
また、資金・税金の問題もあります。
会社の株式が高く評価されると、後継者に多額の相続税がかかることがあります。
納税資金が不足すると、株式の売却を余儀なくされ、経営権が揺らぐ原因となります。
そのほか、被相続人が経営していた会社に後継者がいない、あるいは選定が進まないまま経営者が亡くなると、会社はトップ不在のまま適時適切な運営ができなくなり、廃業に追い込まれるリスクが生じます。
また、経験が乏しい後継者が事業を引き継いだ場合、業績悪化を招くことがあります。
(5)高額な相続税に関するお悩み
日本の相続税制度は世界でも屈指の高税率で、富裕層にとって深刻な課題となっています。
基礎控除の範囲内に収まる一般家庭では、相続税の納税義務が発生しないことが多いため、不満の声はあがらないでしょう。
しかし、遺産の総額が数億円から数十億円以上になる大規模な遺産分割では、当然、相続税に関する悩みが生じます。
相続税の最高税率は55%に達し、適切な対策を講じなければ、相続が発生するたびに資産の半分近くを税金として納めることになりかねません。
「三代で財産が消える」という言葉が示すように、何も対策をせずに相続を重ねれば、築き上げた財産は急速に目減りしていきます。
そして、多くのケースで預金や上場株式等の流動資産よりも、不動産や非公開株など流動性が低く換金が難しい資産が多いことから、納税するための資金を用意することが難しく、相続税対策を何もせずに放置していると相続人が納税で大変な苦労をすることになります。
3 大規模な遺産分割の対応方法
円滑に進めるためのポイントとして、まずは、遺産の範囲に含まれるすべての財産を漏れなく洗い出し、遺産全体を正確に把握したうえで、専門家による適正な評価を行います。
すなわち、現金、預貯金、不動産、株式・有価証券、美術品、事業用資産など、すべてのプラスの財産をリストアップします。
同時に、借金などのマイナスの財産も確認します。
そして、 不動産は不動産鑑定士、事業用資産は公認会計士、美術品は美術鑑定士など、専門家による適正な評価を行います。
そして、全員が納得できる合意形成(遺産分割の成立)を目指します。
協議を円滑に進めるためには、すべての相続人に対して財産情報を公平に開示することで透明性を確保し、不信感の発生を防ぐことが大切です。
相続人の間で意見が対立する場合、特定の財産(自宅など)を特定の相続人が取得し、他の相続人には金銭で代償金を支払う代償分割も有効な方法です。
必要であれば、遺産分割調停や審判に移行することも視野に入れます。
感情的な対立などで協議がまとまらない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停の利用を検討します。
調停でも解決しない場合は、自動的に遺産分割審判に移行し、裁判官が判断を下します。
納税対策も視野に入れる必要があり、相続税の納税資金をどう確保するか、分割案と併せて検討します。
財産評価が複雑になる大規模な相続では、税理士と連携して、不動産の有効活用や事業承継税制などを検討し、相続税の負担を軽減します。
4 大規模な遺産分割を弁護士に依頼するメリット
大規模な遺産分割を弁護士に依頼するメリットは、複雑な手続を円滑に進め、相続人間のトラブルを防ぎ、依頼者の権利を確実に守ることです。
まず、遺産の全体像を正確に把握することは、適切な分割に不可欠ですが、弁護士に依頼すれば、手間のかかる相続財産の調査を全て任せることができますし、弁護士が徹底的に調査することで、遺産の調査漏れによる不公平な分割を防ぐことができます。
次に、大規模な遺産分割では、不動産や非公開株式など、評価が難しい財産が含まれることがあります。
この点、弁護士は専門的な知見や他士業との連携によって、適正な評価を導き出し、依頼者の不利益を防ぐことが可能です。
また、遺言書が存在する場合、その有効性を法的に判断できますので、無効な遺言書に基づいて手続が進み、あとになって全て覆されるというリスクを回避することができます。
そして、冒頭に述べたとおり、大規模な遺産分割では、遺産の額が大きいがゆえに相続人同士の対立が激しくなる傾向があります。
ここでも、弁護士が代理人として交渉することで、冷静かつ客観的な話し合いができますし、弁護士が専門知識を活かし、法律に基づいた主張を行うことで、交渉がスムーズに進みます。
さらに、せっかく遺産分割が成立しても、遺産分割協議書の内容に不備があると、相続登記などの相続財産の承継、名義変更の手続が進められなくなるリスクがあります。
この点でも、遺産分割協議書の作成を弁護士に依頼すれば、法的に有効かつ適切な書類を確実に作成できます。
加えて、遺産分割協議がまとまらない場合、調停や審判に移行することになりますが、弁護士はこれらの手続も代理できるため、依頼者は本来の生活を送りながら最後まで安心して任せることができます。
5 大規模な遺産分割については当事務所にご相談ください
これまで見てきたように、大規模な遺産分割は、遺産の全容を漏れなく把握し、適正な評価を行うことには大変な困難を伴いますし、相続人同士の激しい対立により、遺産分割が難航する可能性はかなり高いといえます。
そのため、相続の専門家である弁護士によるサポートが不可欠といえます。
当事務所にご相談いただければ、大規模な遺産分割について、状況を詳しくお伺いし、最適な解決方法をご提案いたします。
まずは、お気軽にご相談ください。
(弁護士・山口龍介)