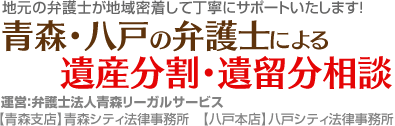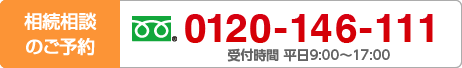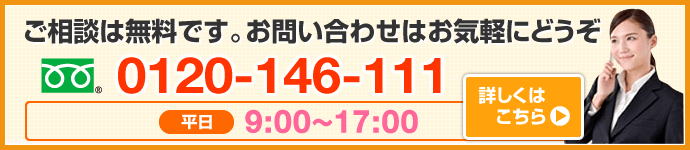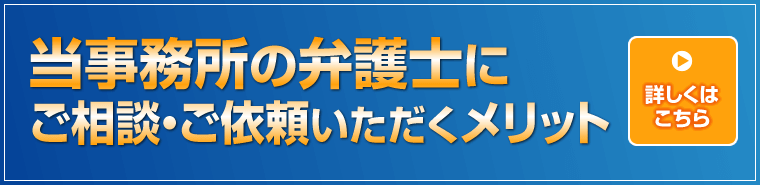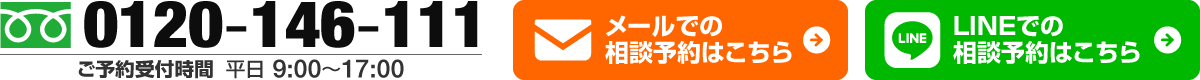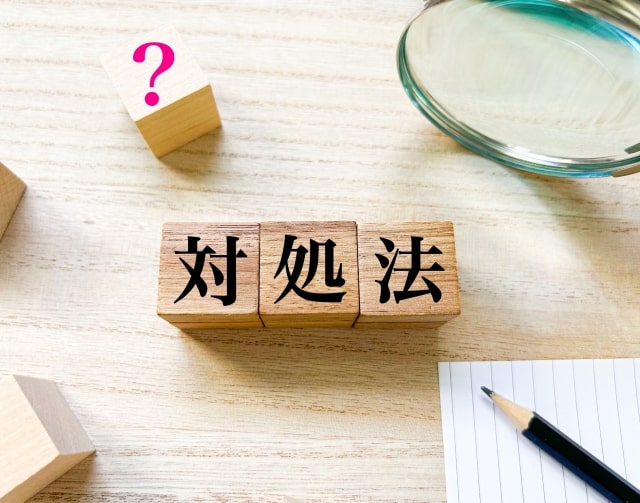
遺産分割は、相続人全員で協議しなければ、成立させることができません。
しかし、現実問題として、あらゆる理由により、遺産分割がすんなりまとまらないことはよくあります。
ここでは、遺産分割が進まない主なケースと、それへの対応について解説していきます。
1 よくある遺産分割が進まないケース
(1)他の相続人と不仲である場合
まず、遺産分割が進まない最も多いケースとして、他の相続人と不仲である場合が挙げられます。
特に、被相続人が存命中は問題にならなかったけれども、相続が発生してから相続人間で不仲になるというケースは珍しくありません。
また、このようなケースでは、感情的な対立が激化し、相続とは関係ない過去の出来事を持ち出すなど本題から徐々に逸れていくことで、およそ話し合いがままならないこともあるでしょう。
(2)一部の相続人と連絡が取れない場合
次に、遺産分割が進まないケースとして多いのが、一部の相続人と連絡が取れない場合です。
前述のとおり、遺産分割協議は相続人全員で行わなくてはなりません。
そのため、仮に相続人の大多数が同じ意向を示していたとしても、一人でも意向を確認できない相続人がいる場合には、どうやっても遺産分割をまとめることができません。
また、これに近いものとして、相続人に全く面識のない人が含まれているケースが挙げられます。
現に、相続手続きを進めようとして戸籍を収集していたところ、被相続人の異母兄弟が見つかった、というケースでのご相談を受けることはよくあります。
このケースでは、心理的にこのような相続人とは連絡を取りづらいことから、結果的に遺産分割を進められなくなる事態に陥りがちです。
(3)財産の範囲が確定できない場合
例えば、よくあるケースとして、被相続人と同居していた相続人が被相続人の預貯金を管理していたため、他の相続人が被相続人の財産を全く把握していなかったというものが挙げられます。
この場合には、被相続人の財産を管理していた相続人が被相続人の通帳の中身をなかなか開示しないという場合があります。
財産の中身が分からない以上、遺産分割は進めようがありません。
また、仮に通帳の開示があったとしても、取引履歴を調べてみると、多額の現金の払い戻しが確認され、財産を管理していた相続人が被相続人の財産を使い込んでいたのではないかと推測される場合があります。
このような場合には、使い込みがあったかどうか相続人間で言い合いとなり、話し合いが進まない場合があります。
(4)遺産の評価に争いがある場合
現金や預貯金と異なり、被相続人の財産に株式や不動産がある場合には、その評価額を正確に定めることは困難です。
特に、被相続人が非上場会社を経営しており、その株式を多数保有している場合には、誰がいくらで取得するのかが今後の会社の帰趨にも影響してくるため、手続きが難航します。
また、一口に不動産と言っても、単なる住居不動産なのか、事業で用いていた不動産なのかによっても評価が大きく変わりますし、その不動産に関して住宅ローンを組んでいたり、事業の担保に入っていたりする場合には、その評価方法は変わってきます。
(5)特別受益や寄与分の主張がある場合
例えば、事業の跡継ぎなどの理由で、特定の相続人のみが被相続人から生前に多額の贈与を受けているケースは珍しくありません。
このような多額の生前贈与は、実質的に相続の前渡しになるため、これを考慮しないまま相続手続きを進めることは、他の相続人との間で不公平が生じます。
このような遺産を被相続人の財産として持ち戻して、相続人の具体的相続分を決める制度を特別受益と言います。
また、被相続人と同居していた相続人が被相続人の療養・介護を一手に担っていたというケースでは、それによって、被相続人の財産の維持や増加という貢献に繋がったということがあります。
その場合には、その分だけ、当該相続人にはより多くの財産を分与すべきとする制度を寄与分と言います。
特別受益についても寄与分についても、そのような主張がなされることは珍しくありません。
もっとも、法的に見れば該当しないものであったとしても、自身の具体的相続分を多くしたいがために、相続人の中にこのような主張をする人が現れたら、特に揉める原因となるでしょう。
2 遺産分割が進まないときの対処法とは
(1)弁護士を依頼する
まず、遺産分割が進まない理由がどのような場合であるにせよ、第三者が間に入ってもらう方法が挙げられます。
第三者が入ることで、感情的な対立を抑えたり、対立点を整理したりして話を進めていくことが期待できます。
そして、このように第三者を間に入れる場合には、法律の専門家である弁護士に相談・依頼するのが確実です(理由は後述のとおり)。
遺産分割に強い弁護士であれば、相続人の間に入って調整することに慣れており、相続人の主張が法的に認められるものかを判断することができます。
また、連絡先が分からない相続人がいたとしても、住所を調べてそこに連絡を取ることで遺産分割を前に進めることができます。
さらには、相手が財産を隠していたり、使い込んでいたりした場合には、同様に預貯金口座の取引履歴を調査し、返還請求の訴訟をするなどの総合的な解決が見込めます。
(2)裁判所の手続きを利用する
弁護士が間に入っても、話し合いでは遺産分割がまとまらない場合もあります。
このように話し合いではまとまらない場合、裁判所に遺産分割調停を申立てて、その中で取り決める方法があります。
遺産分割調停では、調停委員が相続人に対し、遺産分割をするのに必要な書類の提出を求め、相続人それぞれの意見を聞いた上で、主張や争点を整理して遺産分割についての話し合いを進めていきます。
遺産分割調停自体は、あくまで話し合いの手続きではあるものの、裁判所の手続きであることから、相続とは関係ない主張などを排斥して進めていくため、遺産分割協議よりはまとまりやすいものとなっています。
なお、遺産分割調停をやってもまとまらない場合には、遺産分割審判の手続きに移行することになります。
遺産分割審判の手続きは、話し合いではなく、裁判官に遺産分割の内容を判断してもらう手続きとなります。
そのため、一部の相続人が納得しがたい内容になる可能性があるものの、最終的には何かしらの形で遺産分割の内容を取り決めることができる手段となります。
3 遺産分割を弁護士に依頼するメリット
上述のとおり、遺産分割が進まない場合には、遺産分割協議にせよ、遺産分割調停にせよ、弁護士に依頼すると、弁護士が窓口となって対応してもらうことが可能です。
そのため、まず一番のメリットとしては、特に不仲である相続人とのやり取りを一挙に任せることができることから、そういったストレスから解放されるという点が挙げられます。
また、弁護士であれば、遺産の評価額を算出することができますし、特別受益・寄与分に関する正確な知識を有しているため、依頼した相続人にとっては、満足のいく内容で取り決めることが期待できます。
なお、遺産分割を進めるにあたっては、司法書士や行政書士に相談・依頼をすること自体は可能です。
しかし、弁護士と違い、これらに依頼をしたとしても、通知書を送ることしかできず、それ以降の手続き、つまり、相続人の間に入って交渉・調整することは一切できません。
また、遺産分割調停を申立てたとしても、弁護士は調停に同席できますが、これらの資格を有しているだけでは調停に同席できません。
その上、弁護士から見ると、専門家を名乗っているものの、正確に法的知識を有していないと見受けられる方も一定数おり、結局、何も進められなかった、という場合もあります。
このように、弁護士を避けて司法書士や行政書士に依頼して済ませてしまおうとすると、かえって時間がかかり、結局何も進めることができなかったという結果に繋がりかねないため、最初から弁護士に相談・依頼するのが確実です。
4 遺産分割を放置するリスク
(1)名義変更ができない
遺産分割が未了の場合、法的には、遺産が共有状態となります。
そのため、預貯金口座の解約をすることができず、不動産や株式の名義を変更することもできません。
つまり、預貯金を受け取ることができず、不動産や株式についても売却することができないことになります。
その結果、例えば、一部の相続人が被相続人の費用を立て替えていたとしても、その清算をすることができない状態が続くことになります。
また、金融機関にもよりますが、被相続人が死亡してから数年間しか取引履歴を保管していないことがほとんどです。
そのため、遺産分割を放置すると、資料の収集ができなくなり、特別受益などの主張が困難になりかねません。
(2)相続人に変化が生じる
相続手続きが長期化すると、相続人が死亡するリスクが出てきます。
このように相続人の中に死亡した人が出てくると、その死亡した相続人を相続した人との間で遺産分割をしなければならなくなります。
死亡した相続人を相続することを数次相続と言いますが、数次相続の場合、相続人が一人とは限らず、増えていく可能性が出てくるため、放置するにつれて手続きが複雑になります。
また、相続人が死亡するとはいかないまでも、相続人が高齢化して認知症にかかる可能性があります。
認知症の程度によっては判断能力が無くなるため、そのままでは遺産分割を進めることができません。
この場合には、その相続人に成年後見人など財産を管理する者を選任し、その者との間で遺産分割を進めていかなければならず、手続きが大変面倒になります。
(3)相続税の申告
遺産の金額が大きく、相続税が発生する場合には、相続開始から10か月以内に相続税の申告をしなければなりません。
これは、相続開始から10か月以内に遺産分割が成立していなかったとしても、申告しなければなりません。
そのため、放置をしていた場合には、減税特例の適用を受けられず高額な納付金を準備しなければなりません。
5 遺産分割に関するお悩みは弁護士にご相談ください
上記のとおり、遺産分割が進まない原因は多岐にわたっており、遺産分割の成立が一朝一夕にいかないことが多いです。
また、相続人によっては、話すたびに言うことが変わる人がいるなど、遺産分割協議の終わりが全く見えない状況に陥ってしまうことはよくある話です。
このような場合には、もはや相続人同士だけで話し合いをして遺産分割を進めるのはどうやっても不可能でしょう。
そのような場合には、まずは弁護士にご相談することをお勧めします。
当事務所では、これまで多くの遺産分割のご相談を受けており、遺産分割がまとまらない多数の案件を解決してきました。
遺産分割の進め方にお悩みの方は、当事務所にご相談ください。
(弁護士・下山慧)