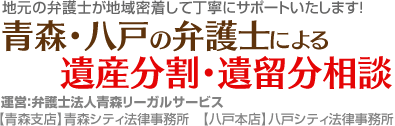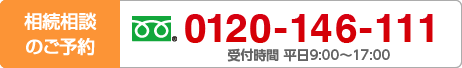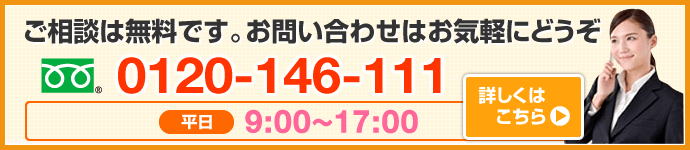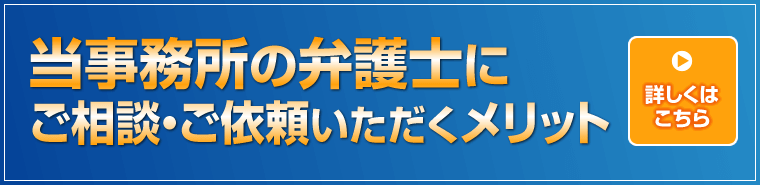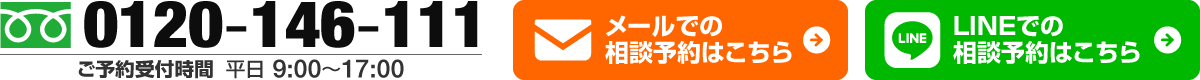1 弁護士に依頼しなくても遺留分調停自体は可能

遺留分侵害額請求は、必ずしも弁護士に依頼しなければならないというわけではありません。
したがって、弁護士に依頼しなくても、遺留分調停自体は可能です。
しかし、法的な知識が不十分であれば、すべてご自身で手続を行うのは、現実的には難しいと考えられます。
遺留分の制度は複雑であり、侵害額の計算、相手方との交渉、調停手続の対応などが必要であるため、弁護士のサポートを受けた方が負担は少ないでしょう。
2 遺留分侵害額請求の流れ
遺留分侵害額請求の手続は、以下のような流れで進めることとなります。
(1)遺留分侵害額請求書の送付
まずは、遺留分の権利者が贈与・遺贈を受けた人に対し、遺留分侵害額を請求する旨の意思表示を記載した請求書を送付します。
遺留分侵害額請求には期間の制限があり(遺留分の侵害を知った時から1年、被相続人の死亡から10年)、遺留分侵害額を請求する意思表示を行ったという証拠を残しておく必要があります。
そのため、遺留分侵害額請求書の送付は、内容証明郵便により行うのが基本です。
(2)遺留分侵害額の計算と具体的な金額の請求
遺留分侵害額がいくらになるかを計算し、具体的な金額の請求を行います。
遺留分侵害額の計算の前提として、相続人の範囲と人数、および相続の対象となる財産がどれだけあるか、を確定する必要があります。
そのため、戸籍謄本類の収集・精査、および相続財産の調査を行う必要があります。
そして、民法の定めに従って遺留分侵害額を計算したら、具体的な金額を請求して協議(話し合い)による解決を目指します。
(3)遺留分侵害額請求調停の申立て
遺留分侵害額請求の協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に遺留分侵害額請求の調停を申し立てます。
遺留分侵害額請求の調停では、調停委員が仲介者となって合意成立に向けた話し合いが行われます。
(4)遺留分侵害額請求訴訟の提起
遺留分侵害額請求調停でも解決できない場合には、遺留分侵害額請求の訴訟を提起することとなります。
遺留分侵害額請求の訴訟は、請求する金額に応じて地方裁判所または簡易裁判所に提起します。
遺留分侵害額請求の訴訟では、裁判官が下す判決により決着することもありますが、裁判官から和解による解決が提示されることも多いです。
各当事者が合意して和解成立となれば解決となり、合意ができなければ判決となります。
3 遺留分調停を弁護士なしで進める方法
遺留分侵害額請求の調停では、弁護士に依頼することが法的に強制されるわけではありません。
そのため、上記のような手続の流れに従ってご自身ですべて対応できるのであれば、弁護士なしで進めることも理屈上は可能です。
しかし、遺留分侵害額請求の調停をご自身で進めることには、以下でご説明するようなリスクがありますので、ご注意いただければと存じます。
4 遺留分調停を自分で進めるリスク
遺留分侵害額請求の調停にご自身で対応することには、次のようなリスクがあります。
(1)正確に手続を進めることが困難である
遺留分侵害額請求の手続は、非常に複雑です。
法律の条文だけでなく、判例などの実務的な知識がなければ、正確に手続を進めることは困難です。
法律の専門家でない方がご自身で遺留分侵害額請求の手続を行えば、適正な解決とならないおそれがあります。
(2)手間と時間を要し多大な負担がかかる
遺留分侵害額請求では、相続人・相続財産の調査、遺留分侵害額の計算など、複雑で手間と時間がかかる事務対応が不可避です。
また、ご自身で遺留分侵害額請求の手続を行う場合、相手方との交渉もご自身で行う必要があります。
このように、ご自身で手続に対応しようとすれば、多くの手間と時間がかかりますし、プレッシャーやストレスも大きいでしょう。
(3)調停・訴訟の手続対応に困難を伴う
遺留分侵害額請求の調停では、調停委員を十分に説得できるだけの主張の整理や証拠の提出が必要となります。
また、遺留分侵害額請求の訴訟は、民事訴訟法に従った厳格で複雑な手続対応が求められます。
法律の専門家でない方が家庭裁判所での調停や訴訟の手続に適切に対応していくことは、極めて困難であると言えます。
5 遺留分調停を弁護士に依頼するメリット
遺留分侵害額請求の調停をご自身で進めることには上記のようなリスクがあるのに対し、弁護士にご依頼いただけば以下のようなメリットがあります。
(1)手続を正しく円滑に進めることができる
弁護士は、法律および法的手続の専門家です。
弁護士であれば、遺留分侵害額請求の制度に精通し、調停や訴訟を含む手続の対応にも慣れています。
そのため、弁護士に依頼することにより、安心してスムーズに手続を進めることが可能となります。
(2)面倒な手続や相手方との交渉を任せることができる
遺留分侵害額請求では、必要な資料の収集、遺留分侵害額の計算、各種書類の作成など、面倒な事務手続が数多く発生します。
また、相手方との交渉も必要となります。
この点、弁護士に依頼すれば、面倒な事務手続を一任することができますし、ストレスのかかる相手方との交渉も弁護士を窓口とすることができます。
(3)調停・訴訟の手続にも安心して対応することができる
遺留分侵害額請求では、調停や訴訟が必要となることも少なくありません。
調停や訴訟の手続に適切に対応するためには、法的な知識と経験が不可欠となります。
法律の専門家である弁護士にご依頼いただけば、複雑な調停・訴訟の手続にも難なく臨むことができます。
円滑に、かつ有利に手続を進められる可能性が高いでしょう。
6 遺留分に関するお悩みは当事務所にご相談ください
以上のとおり、遺留分侵害額請求の手続は複雑であり、遺留分調停を自分で進めることには様々なリスクがあります。
弁護士に依頼するメリットは非常に大きいため、遺留分侵害額請求についてお悩みの場合には、まずは弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
当事務所では、遺留分侵害額請求に関するご相談・ご依頼を承っており、解決実績も豊富にございます。
遺留分侵害額請求についてご不明のことがありましたら、お気軽に当事務所にご相談いただければと存じます。
(弁護士・木村哲也)