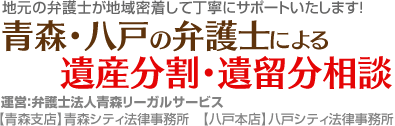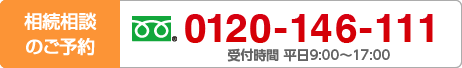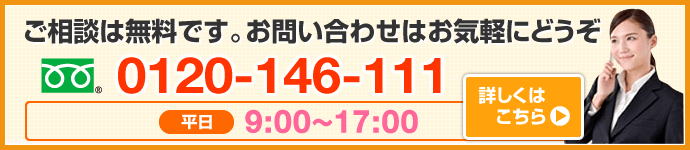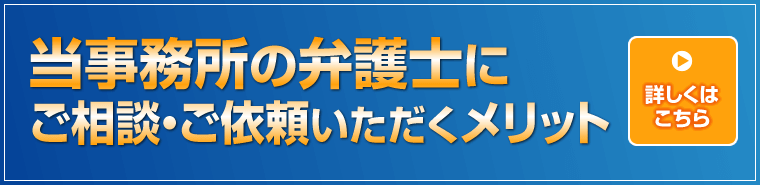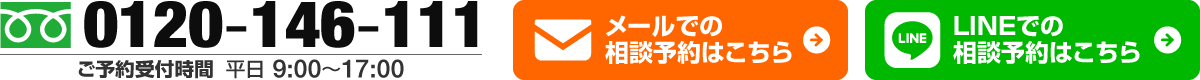株式には、東京証券取引所などで売買されている上場株式と、家族経営の会社のように株式市場で売買されていない非上場株式があります。
被相続人が保有している株式がいずれであるかによって、相続方法と評価方法が異なるため、以下でご説明させていただきます。
1 株式の相続手続の流れ
被相続人が保有している株式を相続するためには、被相続人が保有している株式を調査し、その株式の名義人を被相続人から相続人に変更する必要があります。
この、調査→名義変更、という流れは上場株式であろうと非上場株式であろうと変わりません。
ただし、上場株式か非上場株式かで、それぞれの具体的な手続きが異なります。
以下で詳述いたします。
(1)株式の調査
【①上場株式の場合】
まず、被相続人が株券を保有していれば、その会社の株式を保有していることが分かります。
もっとも、上場株式については、現在は証券会社等が電子管理の方法で株式を管理しているため、実際には株券が見つかる可能性はほぼありません。
したがって、証券会社に問い合わせて、残高証明書を発行してもらうことが一番手っ取り早い方法であり、これによって株式の銘柄や株数を把握することができます。
被相続人が証券会社を利用していれば、証券会社からの郵便物が届いていたり、預貯金の通帳に配当金などの入金が確認できたりする場合があるため、それにより被相続人がどこの証券会社を利用していたのか推測することができます。
もっとも、被相続人が利用していた証券会社に心当たりがなく、郵便物等を探しても被相続人がどこの証券会社を利用していたか判明しない場合もあると思います。
このような場合には、「証券保管振替機構」(通称:ほふり)に情報開示請求をすることで、被相続人がどこの証券会社に証券口座を保有していたか調べることができます。
ただし、情報開示請求によって判明するのは、「どこの証券会社に証券口座を有していたか」という点に限られ、株式の銘柄や株数は開示されません。
したがって、最終的には、情報開示請求によって判明した証券会社に問い合わせて残高証明書を発行してもらう必要があります。
【②非上場株式の場合】
一方で、上場株式の場合と異なり、証券会社での管理がなされていることはないため、株式の調査をすることは困難です。
したがって、非上場株式の場合には、被相続人が株券を保有しているかどうかを調査することが重要になってきます。
特に、非上場株式の場合、未だに株券発行に関する規定(定款)を変更していない会社もあるため、被相続人が金庫などで保管している可能性が考えられます(ただし、株券発行会社であっても実際には株券を発行していない会社があったり、非上場株式であっても株式を電子管理していたりする会社もあります)。
また、非上場株式というのは、そもそも家族間・親族間で会社を経営している会社によって発行されている場合がほとんどです。
つまり、家族・親族に会社を経営していたり、役員になっていたりする人がいれば、被相続人がその会社の株式を保有している可能性があります(逆に、身近にこのような人がいなければ、非上場株式を保有している可能性は低いでしょう)。
したがって、このような方がいるのであれば、まずはその会社に株式の有無を問い合わせる方法が直接的です。
(2)名義変更
【①上場株式の場合】
株式の調査が終了したら、(その株式を発行している会社ではなく)証券会社に対し、名義変更を希望する旨の連絡をします。
連絡した場合、証券会社からは、名義変更に必要な書類の説明を受けることができると思います。
通常は、戸籍関係、住民票、本人確認書類、遺産分割協議書など他の相続手続でも一般に必要とされている書類と同様の書類が必要になるでしょう。
また、その証券会社で用いている書式での申請書等の提出を求められることになるでしょう。
その上で、実際に株式を相続するには、名義を書き換えた株式を相続人の証券口座に振り替えてもらう必要があります(被相続人名義の証券口座を流用したり、被相続人名義の証券口座の名義を変更したりすることはできません)。
このように、相続人は、必ず、自分名義の証券口座を準備する必要があります。
【②非上場株式の場合】
これに対し、非上場株式の場合には、その株式発行会社に対して、名義変更を希望する旨の連絡をします(名義変更に必要な書類は、上場株式の場合とほぼ同様でしょう)。
必要な書類が充足していると判断された場合、株式発行会社に対して、株主名簿に記載してもらうよう求めることができるので、株主名簿に正しく記載されたかどうか確認するようにしましょう。
2 株式の分割方法
相続人が複数人いる場合には、遺産分割により、株式を相続する者を決める必要があります。
株式の分割方法には、①現物分割、②換価分割、③代償分割の3つの方法があります。
これらの方法はどれか一つに絞らなければならないわけではなく、例えば、複数の株式がある場合には、一部は現物分割にして他は換価分割にする、というように分割方法を織り交ぜることも可能です。
なお、これらの分割方法は、上場株式と非上場株式との間で変わるところはありません。
(1)現物分割
現物分割とは、株式を金銭に換えずにそのまま相続する方法を指します。
典型例は、被相続人が株式を3000株保有していた場合、子ども3人で1000株ずつ相続するといった方法です。
他にも、被相続人が複数の銘柄の株式を保有していた場合、それぞれが別々の銘柄の株式を相続するといった方法も現物分割となります(ただし、銘柄ごとに株価に差があれば、その株価も勘案して分割する必要があるでしょう)。
このように、現物分割は金銭に換える必要がないことから、その分割自体は簡易です。
もっとも、現物分割の中に非上場株式が混ざっている場合、単純に株式数や評価額といったことだけを考慮して決めるのは注意が必要です。
というのも、非上場株式の場合、発行済み株式総数が多くないことから、会社の代表取締役を務めていた被相続人が大多数の株式を有しているケースは珍しくありません。
その場合、その株式を一人の相続人に集める形で現物分割したとすると、その相続人が会社の議決権の多数を有することになります。
逆に、法定相続分に応じて現物分割した場合も、株式数が分散され、議決権も分散されることになります。
このように、非上場株式の分割は、その後の会社の経営の帰趨に影響を及ぼすため、慎重に行う必要があります。
(2)換価分割
換価分割とは、株式を売却して、そこで得た売却代金を相続人間で分配する方法を指します。
具体的には、前述のとおり、一旦、代表相続人に株式の名義変更をしてから、売却後に、売却代金を相続人に分配します(売却代金の分け方については、法定相続分に従って分配するのが一般的でしょう)。
なお、非上場株式の場合、株式の売却について、会社の定款で譲渡制限が定められている可能性があります。
この場合、売却先を探した後、会社にその売却の承認を得る必要があるといったように、手続きが複雑になります。
また、当然に会社が株式を買い取ってくれるとは限りません。
そのため、非上場株式を換価分割するにあたっては、事前に会社への確認をしておくようにしましょう。
(3)代償分割
代償分割とは、特定の相続人に株式を相続させ、株式を相続した相続人が他の相続人に対し、取得した株式の評価額相当の金銭を支払う方法を指します。
実際の相続の場面では、例えば親族が経営する会社の経営には関心がない相続人がいる場合など、株式の取得を希望しない相続人がいることは珍しくありません。
このような場合には、他の相続人が株式を取得する代わりに、その相続人には金銭や不動産を取得させるといった調整が行われます。
このように、代償分割は、株式の取得を希望する相続人がいれば、遺産全体を柔軟に分割することができる方法として、もっとも用いられる分割方法です。
3 株式の評価方法
(1)上場株式の場合
上場株式の場合、株式の評価額は市場で取引されている金額になります。
そのため、インターネットで検索すれば株価は容易に判明します。
また、前述したように、証券会社から残高証明書を発行してもらえば、その時点の株価が判明します。
(2)非上場株式の場合
これに対し、非上場株式の場合、市場での取引がなされていないことから、株式の評価額を算出するのはかなり困難です。
とはいえ、通常、どんなに小さい会社であっても会計資料を作成しています。
そのため、基本的にはこの会計資料を基に株価を算出していくことになります。
ただし、株価の算出方法は、業種や会社の規模を勘案することがあり、唯一絶対の算出方法はありません。
もっとも、比較的小規模の会社であれば、会社の資産から負債等を控除して算出された純資産価額を発行済み株式数で除して評価する「純資産価額方式」によって算出することが多いように見受けられます(相続税を算出する際もこの方法が用いられる場合があります)。
この方法であれば、決算書や確定申告書などの算出に必要な資料を準備すれば、付き合いのある税理士に依頼することで、比較的容易に株価を算出することができるでしょう。
一方で、他の相続人が純資産価額方式で算出することに不服を訴える場合もあり得ます。
このような場合には、株価の算出にあたり、もはや相続人間の話し合いで取りまとめていくことは困難になりますので、遺産分割調停などの裁判所の手続きをしていくことを検討しなければなりません。
裁判所の手続きをしていく場合、裁判所が選任した鑑定人が株価を算出することになりますので、これによって算出された株価を基準として取りまとめていくことになると存じます。
4 相続でお悩みの方は当事務所にご相談ください
相続財産に株式が含まれている場合、往々にして被相続人が多くの遺産を有しています。
そしてこのような場合、被相続人の生前は揉め事がなかったとしても、死亡後に相続人間で揉めることは珍しくありません。
また、本件では株式について解説いたしましたが、株式だけでなく不動産についてもほぼ同様であり、やはりその評価額や分割方法も揉める原因の一つと言えます。
しかし、不動産の分割については評価方法が多数あり、直感的に理解しやすい部分である一方で、株式の分割については株式を触ったことがない方にとっては、敬遠したい部分といえるでしょう。
こういったことから、相続財産に株式が含まれている場合には、株式の分割に精通した弁護士にご相談することを強くお勧めします。
株式の分割の経験が乏しい弁護士だと、特に非上場株式の場合、株価算定のプロセスさえ理解していない方もおり、このような弁護士にご相談することは危険です。
当事務所では、これまでに上場株式はもちろん、非上場株式の遺産分割について多数の経験があり、これまで適切に株価を算定して遺産分割をしてきた実績がございます。
相続財産に株式が含まれている場合には、一度、当事務所にご相談ください。
(弁護士・下山慧)